- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
コラム 「特許マップを活用しましょう」 技術士(電気電子部門) 肥沼 徳寿
「特許マップ」という言葉を耳にしたことがあると思いますが活用している方は多くないようです。
「特許マップとは膨大な特許情報を、特定の利用目的に応じて収集・整理・分析・加工し、かつ図面、
グラフ、表などで視覚的に表現したもの」です。私は「特許情報」の価値は予想以上に高いことを強調
したいと思います。すなわち ①1.5 年経過後に公開されるとはいうものの産業技術に裏付けられている
②他の手段では得られない信用性がある③一定の規格によって統一されている④グローバルな情報で
ある⑤未来志向の情報である等々です。
特許マップは次のようなことに利活用が可能です。「技術トレンド」を知る「競合他社動向」
「技術開発ヒント」「他社権利状況」、「各社注力分野と度合」等です。
卑近な使い方では他社の技術者数もおおよそ推定することもできます。
すでに特許電子図書館を利用している方、これから利用しようとする
方々、特許マップの作り方は難しいものではありません。まずは手作りで始めることをお薦めします。
最近では特許マップを作成するソフトも出回っています。
すこし慣れてきたらそれらを利用するのも良いでしょう。
「特許情報」は宝の山であり「特許マップ」と言う加工によって御社の行く手に新たな羅針盤が加わります。
気になる用語 「MOT(技術経営)とは」 技術士(電気電子部門) 平田 滋昭
語源は、米国の大学におけるビジネススクールなどの講義名ですが、MOT(Management Of Technology) といういい方が普及してきたのは、90 年代に入ってからです。日本では、「技術経営」と訳さています。 MOTは 90 年代米国の未曾有の長い好況を支えるものとなりました。一方、90 年代の日 本の企業は、 “失われた 10 年”と呼ばれる苦境の時代でした。中小企業においても、系列化の庇護はな く、?子高齢化による技能者枯渇、中国への移行に伴う国内の空洞化、製品競争の激化、など解決すべ き課題が山積みされています。日本は「課題大国」といわれています。これらの課題を解決し、次の成 長時代を築いていくものは、米国と同様に、技術革新や創業型企業を主導する「MOT(技術経営) 」 です。MOTの目的は「技術投資の費用対効果を最大化すること」または「技術を活用して経営を行う こと」です。中小企業も「MOT(技術経営) 」を学び経営を革新して行かねばならないでしょう。
連載解説 サポーティングインダストリー(第3回最終回) 技術士(機械部門) 武藤 文男
我が国製造業の国際競争力を強化し、新たな事業の創出を図って国民経済の健全な発展に寄与するた
め、 “中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(略称:中小ものづくり高度化法) ”が平成
18年 4月 26日公布、6月 13日施行されました。
第1回解説では法の背景となった「新産業創造戦略 2005」に示された中小企業のものづくり基盤技術
(鋳造、鍛造、めっき、プレス加工、金型等“サポーティングインダストリー”と称す)の高度化に関
する支援策とその技術の活用を目指す 7 つの成長分野を紹介し、第2 回解説では横断的な重要政策として
人材の育成・強化、知的財産重視の経営促進について概要を紹介しました。
我が国の製造業は約 56 万社あり、そのうちの 99%以上が中小企業から構成されて 660 万人の雇用を
創出しております。研究開発型、完成品生産型、特定部品製造に特化した企業、特定加工に特化した企
業等多様な類型が存在し、ものづくりに関する高度な技術水準を実現している企業が多く存在しており
ます。その中でも特定のものづくり基盤技術を有する中小企業(川上中小企業という)が大学等と連携
して高度な技術水準を実現し、成長が期待される新分野の製品を製造する大手企業(川下製造業者とい
う)と緊密に連携して、付加価値の高い製品を企画・設計・製造して新たな産業を構築しようというの
がこの法の狙いです。法の内容、事業展開等については中小企業庁ホームページに逐一発表されること
から URL を毎回ご紹介しておきましたが、今回は最新(平成 19 年 2 月 13 日)のホームページから得
た主な情報を以下にご紹介します。
(1) 「中小ものづくり高度化法」の円滑な施行のため「戦略的基盤技術高度化支援事業」の研究開発テ
-マ公募の案内(公募期間:平成 19 年 4 月下旬~5 月中旬)
法の各種支援を受けるために、この特定研究開発計画の申請、認定取得が必要です。
(2)最新の特定ものづくり基盤技術(粉末冶金、溶接に係る技術が加わり 19 技術)
以上で本連載解説を終わります。ご質問は“かわさき技術士クラブ”までお寄せ下さい。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー]
| メニュー | 日 時 | 内 容 |
| 平成18年度セミナー (9階 第2研修室) | 3月14日(水) 18:00~20:00 |
「技術経営のすすめ ~提言・中小企業の新製品開発」 技術士(機械部門)武藤 文男 |
| 12月 3日(木) 18:30~20:30 |
「ものづくり社員の心得 ~人がものをつくる~」 技術士(経営工学部門)佐藤 幸雄 |
[支援事業]
| 技術士による 技術窓口相談(無料) |
毎週金曜日 13:30~16:30 |
3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日 4月6日、4月13日、4月20日、4月27日 |
| ワンデイコンサルティング (無料) |
随 時 | ・派遣は、川崎市内の中小企業で1日(2時間)程度 ・派遣回数は、同一年度で1企業1回 |
| 専門家派遣(有料:半日 8,000円、1日 16,000円) | 随 時 | ・派遣回数は,川崎市内の中小企業で1企業あたり全日(6時間)の場合10回,半日(3時間)の場合は20回まで |
中小企業サポートセンターは、中小企業を応援する総合的な支援機関です。
主な支援事業は次のとおりです。どうぞご利用ください。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
【問い合わせ先】〒212-0013 川崎市幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館6階
E-mail: f-mutoh@df6.so-net.ne.jp
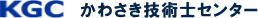
 技術支援ニュース
技術支援ニュース